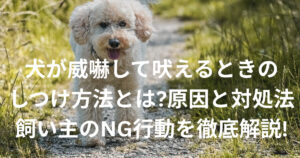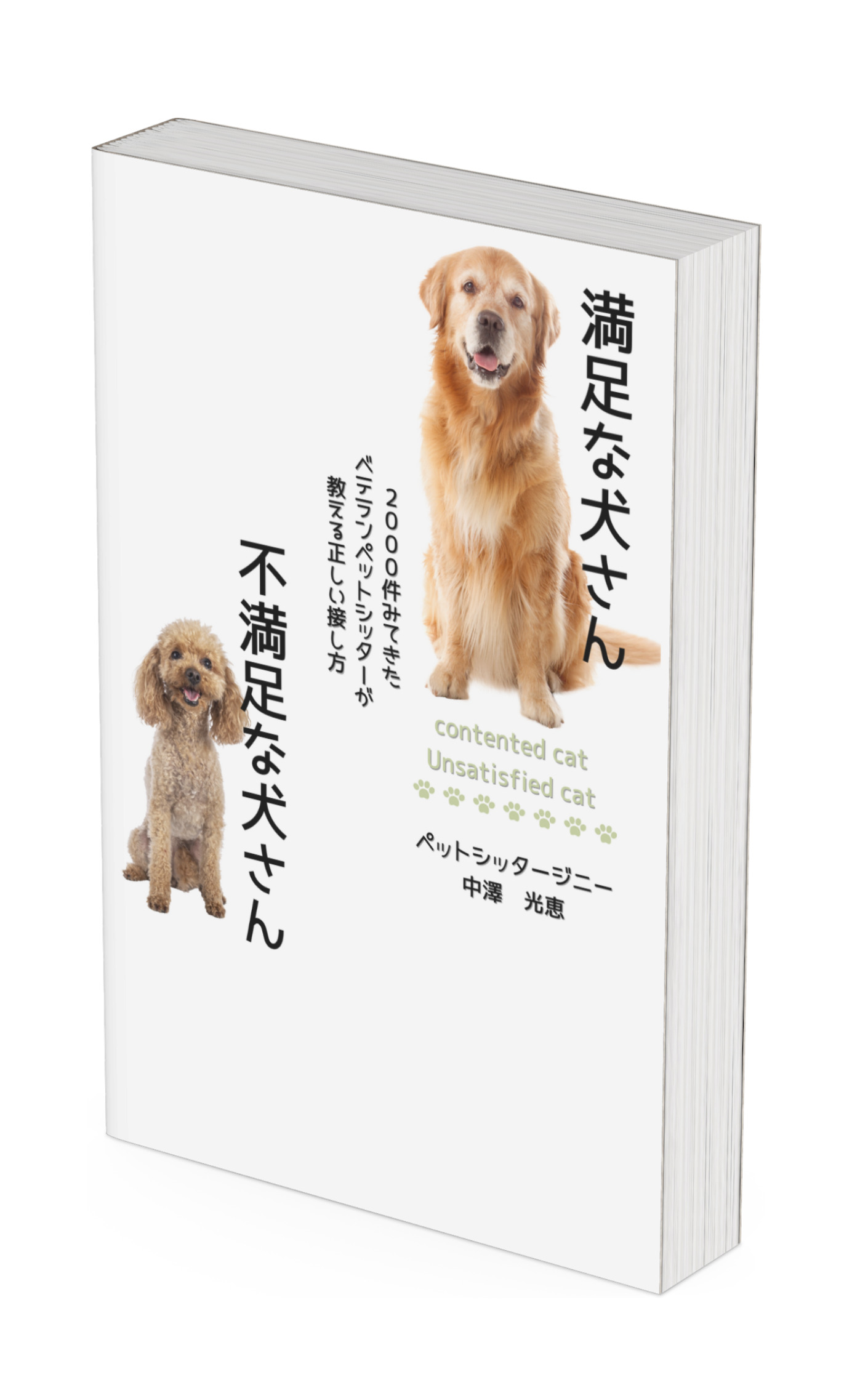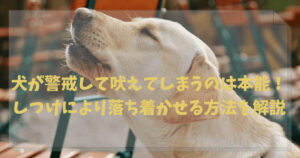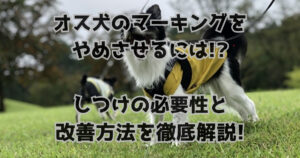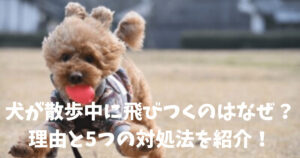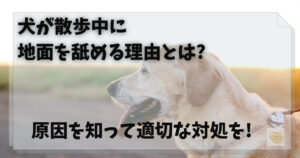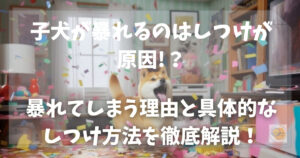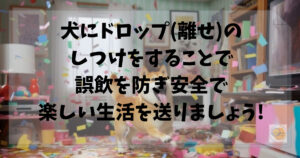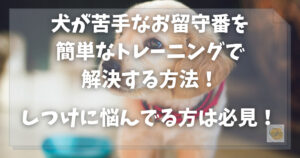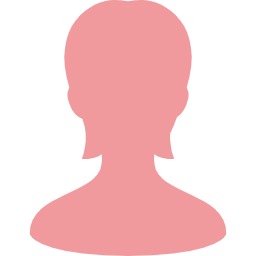 読者様
読者様子供にせがまれて犬を飼ったけど、近づくと怖がってしまうの。
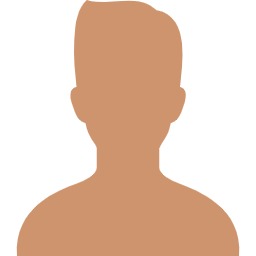
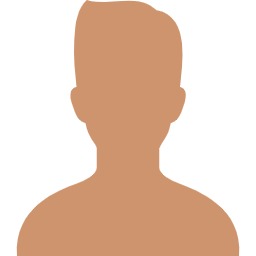
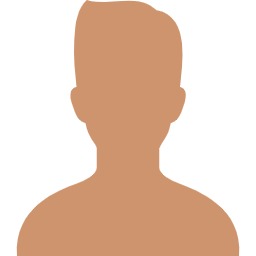
ドッグランに行っても他の犬に近寄らないんだ…



ビビリなワンちゃんに関するお悩みはとても多いんですよ。
焦らずじっくりワンちゃんと向き合うことで克服していきましょう。
犬を飼い始めたけれど、想像していたように元気いっぱいに遊ぶわけではなく、物音や人、他の犬に対して過敏に反応してしまう…。
そんな「ビビリ」なワンちゃんに戸惑いを感じている方も多いのではないでしょうか?
この記事では、犬の気持ちに寄り添いながら、怖がりな性格のワンちゃんとどのように付き合い、しつけをしていけばいいのかを解説します。
ぜひ最後までお読みください。
ビビリな犬の特徴とその行動


ビビリな犬とは、警戒心が大きく、刺激に対して過剰な反応をします。
具体的にどんな行動をするものなのでしょうか?
その特徴は主に2つあります。
- 見知らぬ人や初対面の犬に反応するもの
- 慣れない環境に反応するもの
見知らぬ人や初対面の犬に反応するもの
見知らぬ人や犬など、社会的なものから受ける刺激に反応します。
外出時などに、飼い主さんのひざに乗ってきたり抱っこをせがんだりします。
また、公園などで他の人や犬とすれ違うだけでも、怯えて飼い主の後ろに隠れたり、尻尾を丸めて震える行動も見られます。
見慣れない人、犬がそばにいるときなどにこのような行動を取ることが多い場合は、不安や恐怖を感じている可能性があります。
慣れない環境に反応するもの
騒音や、初めて接する環境に反応するものです。
ドアの開閉音、車のクラクション、インターフォンの音などに対してビクッとしたり、大声で吠えたりします。
花火や雷などの爆音の場合には、吠えたりするほか、クレートやベッドに逃げ込んでしまう犬もいます。
自分の周囲で何か変わったことが起こることで、不安やストレス、恐怖を感じています。
犬が怖がりになってしまう主な原因


それでは、どうして犬は「ビビリ」になってしまうのでしょうか?
ここでは、その原因をみていきましょう。
- 他の犬や人と接する経験値が少ない
- 慎重な性格
- 過去のトラウマがある
- 飼い主の不安な態度に反応する
他の犬や人と接する経験値が少ない
子犬の頃に社会化の機会が少なかった犬は、他者との関わり方がわからず、不安を感じやすくなります。
特に、ペットショップで長期間過ごした犬や、外での散歩経験が少ない犬は注意が必要です。
慎重な性格
人間と同じく、犬にも性格があります。
中には元々慎重でおっとりした性格の犬もおり、新しい環境や人に慣れるまでに時間がかかってしまいます。
また、母犬が臆病で不安定な気質だと、その気質を引き継いでいる場合もあります。
過去のトラウマがある
保護犬など、過去に虐待を受けた、または極端に不安定な環境で育った犬は、トラウマによってビビリになっている場合があります。
急に手を出される、声を荒げられるなどに過剰に反応してしまいます。
また、輸送中や飼育前に何らかのトラウマを抱えてしまうこともあります。
何かのポイントで急に怖がるしぐさを見せる場合は、トラウマがある可能性が高いので、原因をよく調べて対処しましょう。
飼い主の不安な態度に反応する
犬は飼い主の気持ちにとても敏感です。
飼い主が「怖がっている」と感じてしまうと、犬自身も不安を感じてしまいます。
飼い主の気持ちが無意識のうちにワンちゃんのビビリを強化してしまうこともあります。
ビビリな犬への接し方


元々の犬の性格以外にも、環境からも影響を受けるなど、様々な要因から犬はビビリになってしまうことが分かりました。
ここからは、ビビリな犬の接し方、合わせて子供や他の犬と接する時の注意点を5つのポイントを挙げてお話します。
- 犬のペースを尊重してあげる
- 安心できる居場所を作る
- 成功体験を積ませる
- 子供が接するときの注意点
- 他の犬と接するときの注意点
それぞれお話していきます。
犬のペースを尊重してあげる
無理に慣れさせようとするのではなく、犬自身のペースで慣れていけるようサポートしてあげましょう。
無理強いは逆効果になることが多く、かえって恐怖心を強めてしまいます。
安心できる居場所を作る
家の中にクレートやベッドなど、落ち着ける”自分の居場所”を用意してあげましょう。
そこでは決して無理に引っ張り出したりせず、犬がひとりで安心できる空間として守ることが大切です。
自分の居場所で寝ていたり、くつろいでいるワンちゃんを邪魔するのもやめましょう。
成功体験を積ませる
例えば、散歩中に他の犬とすれ違っても怖がらずに歩けたときや、来客の足音に過剰に反応しなかったときなど、小さな「できた!」を見逃さず褒めてあげましょう。
自信を育てることがビビリ克服のカギです。
しかし、犬が怖がっているときに優しい言葉をかけ続けると、「怖がると優しくしてもらえる」と勘違いしてしまうので、できたときに褒めるにとどめておきましょう。
子供が接するときの注意点
子供は犬がかわいくてつい追いかけたり触りすぎたりしがちですが、怖がりな犬にとっては恐怖の対象になることもあります。
子供とはいえ、犬よりは大きいので、撫でようと手を出すだけで怖いと思ってしまうこともあります。
犬のスペースを侵害しない、寝ているところを邪魔しないことも大切です。
まずは子供にも犬の気持ちを尊重し、優しく接することを心がけてもらいましょう。
他の犬と接するときの注意点
無理に他の犬に近づけるのは避けましょう。
犬同士にも相性がありますし、最初は距離を保ちつつ、徐々に距離を縮めていくようにしましょう。
信頼できる犬との交流を通じて、自信を育てることができます。
ビビリな犬のしつけ方のコツ


ビビリな犬も、トレーニングによって怖がりを克服することも可能です。
大切なのは、ワンちゃんの気持ちになって、焦らずに寄り添っていくこと。
こちらの具体的なしつけ方4つのコツをお伝えしていきます。
- 怖さを少しずつ慣らす
- 褒めて自信を与える
- 構い過ぎない
- 飼い主が不安定にならない
怖さを少しずつ慣らす
「馴化(じゅんか)」という方法があります。
怖がる対象を少しずつ見せたり聞かせたりしながら、徐々に慣れさせていく方法です。
無理のない範囲で、短時間から始めましょう。
音に敏感なワンちゃんなら、苦手な音を聞かせた後におやつを与えるなど、音に対する恐怖心を安心感に変えてもらうようにします。
他の犬が苦手なワンちゃんなら、離れたところから他の犬を見ることから始めて距離をだんだん縮めていきましょう。
ドッグランなら最初は柵越しで見学することから始めます。
いずれも焦らず徐々に行っていきましょう。
褒めて自信を与える
例えば、「おすわり」「ふせ」など、簡単な芸でもいいので、覚えさせます。
覚えたら、よくできたことをたくさん褒めてあげましょう。
一見どんな犬でもできる簡単なことのように思いますが、この小さな体験を積み重ねていくことで、大きな自信につながってきます。
構いすぎない
怖がっているからといって、飼い主さんが過剰にかまいすぎるのも逆効果です。
犬は「怖がっていると飼い主さんがずっとそばにいてくれる」と学習してしまい、自立の妨げになってしまいます。
ついかわいそうに思ってしまいますが、ほどよい距離感を大事にしましょう。
また、怖がる対象物を前にすると、サッと抱き上げて優しくしてしまったりするのも、犬がビビリを克服する機会を奪う結果になりかねません。
飼い主が不安定にならない
ビビリな犬にとって、飼い主の安定感は何よりも重要です。
どんな状況でも「大丈夫だよ」と安心感を与えられる存在であることが、犬の信頼を育てます。
まずは飼い主さん自身が落ち着いて行動しましょう。
まとめ:ビビリもひとつの個性
ここまで、ビビリな犬について、その原因、接し方、しつけ方のコツについてみてきました。
ビビリな犬は、以下のような行動の特徴があります。
- 見知らぬ人や初対面の犬に反応するもの
- 慣れない環境に反応するもの
怖がったり吠えたりする、その原因は4つありました。
- 他の犬や人と接する経験値が少ない
- 慎重な性格
- 過去のトラウマがある
- 飼い主の不安な態度に反応する
また、接するときの注意点は、次のようなものがありました。
- 犬のペースを尊重してあげる
- 安心できる居場所を作る
- 成功体験を積ませる
- 子供にも犬の気持ちを尊重し優しく接してもらう
- 他の犬とは最初は距離を取り、徐々に近づいていく
具体的なしつけのポイントは以下の4点がありました。
- 怖さを少しずつ慣らす
- 褒めて自信を与える
- 構い過ぎない
- 飼い主が不安定にならない
怖がりな犬を見て「うちの子はダメだ」と思ってしまうこともあるかもしれません。
でも、慎重で打ち解けるのに時間がかかるのも、大事なひとつの個性です。
大切なのは、その子の性格を受け入れ、無理なく寄り添いながら過ごしていくことです。
焦らず、ゆっくりと時間をかけて信頼関係を築いていけば、少しずつでも変わっていきますよ。
あなたとワンちゃんの関係が、少しでも穏やかで安心できるものになりますよう応援しています。